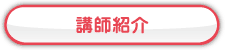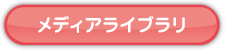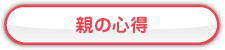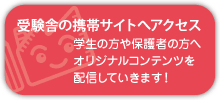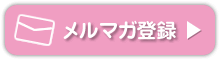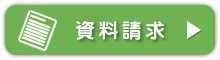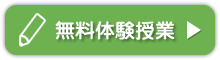メディアライブラリ
vol.8 メディアライブラリ
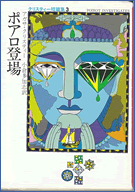
ポアロ登場
アガサ・クリスティー著小学生の頃から私はミステリーが大好きでした。その結末をいち早く知りたい一心で、ご飯の時間も読みながら食事をする、というお行儀の悪いことをしながら、購入したその日のうちに一冊まるまる読み終える…、ということをよくやっていました。(お行儀の悪いことをしても、本を読むことに関しては寛容だった母に感謝です。)
小・中学生の時は「ルパン」シリーズ(アニメのルパン3世ではない)や「シャーロック・ホームズ」シリーズをよく読んでいましたが、高校生の時にちょっと大人な感じがして今まで手を出したことがなかったアガサ・クリスティーの小説を読み始めました。この「ポアロ登場」はそのとき初めて購入したものです。
舞台は1900年代初頭のイギリス。「ポアロ」とはちょっと自意識過剰だけど、「灰色の頭脳」を持つ明晰で優秀なちょび髭を生やした探偵です。実は中学生のとき、この「ポアロ」シリーズのドラマをNHKで放映していたため、「ポアロ」自体には私は大変なじみがありました。
しかし、本を読み進めていくとドラマの「ポアロ」とは異なる楽しみが出てきました。それは「伏線を見つけること」です。ドラマでも伏線は張られているのですが、それはセリフの言い方やカット割等で演出者の意図が反映されています。よって見ていると「何かこれ気になるな…」と思っていたことがトリックにつながっていたりします。ですが、本の中では、文字で滔々と説明されているため、注意深く見ていないと伏線に気付かないのです。その伏線に気付き、犯人やトリックがわかり、「すっきり!」と感じる瞬間、それこそがミステリーの醍醐味なような気がするのです。
この「能動的な読み方」、これは文章を読む上で最も大切なことだと、国語を教えている私は思っています。それを楽しみながらできる、それがミステリーだとも思います。 この「ポアロ登場」は短編集なので、伏線を見つけて結末に至るまでが大変早いです。本や文章を読むのが苦手だと思っている人には読みやすいと思います。国語の教科書や入試にはほとんど登場しない「ミステリー」、ぜひ試しに読んでみてください。

- Vol. 01 6月「人生の地図」 紹介講師 山田 尚史先生
- Vol. 02 7月 アニメ 「攻殻機動隊」 紹介講師 鈴木 浩之先生
- Vol. 03 8月「包帯クラブ」 紹介講師 相羽 寛志先生
- Vol. 04 9月 映画 「ショーシャンクの空に」 紹介講師 伊藤 幹幸先生
- Vol. 05 10月「100万回生きた猫」 紹介講師 大吉 健介先生
- Vol. 06 11月「モモ」 紹介講師 栗本 綾佳先生
- Vol. 07 12月「こんなに面白かった「百人一首」 紹介講師 藤田 賢二先生
- Vol. 08 1月「ポアロ登場」 紹介講師 小池 祐子先生
- Vol. 09 2月「栃木が日本一だ!」 LINK TOCHIGI BREX 2009-2010 紹介講師 小川 智行先生
- Vol. 10 3月「生物と無生物のあいだ」 紹介講師 加納 麻菜実先生
- Vol. 11 4月「HI5!」 紹介講師 山田 尚史先生
- Vol. 12 5月「大地の子」 紹介講師 小池 祐子先生
- Vol. 13 6月「コマ大数学科 特別集中講座」 紹介講師 小川 智行先生
- Vol. 14 7月「世界で一番美しい元素図鑑」 紹介講師 加納 麻菜先生
- Vol. 15 8月「岳物語」 紹介講師 相羽 寛志先生
- Vol. 16 9月「虚構新聞」 紹介講師 大吉 健介先生
- Vol. 17 10月「八十日間世界一周」 紹介講師 藤田 賢二先生
- Vol. 18 11月「アインシュタイン150の言葉」 紹介講師 小川 智行先生
- Vol. 19 12月「イリュージョン」 紹介講師 山田 尚史先生
- Vol. 20 1月「ビロードのうさぎ」 紹介講師 加納 麻菜実先生
- Vol. 21 2月「浅田真央 そして、その瞬間へ」 紹介講師 小池 祐子先生